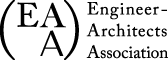/ all
/ all
2011.06.01
01-3|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その3(最終回)
吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)
5.石井樋の復元設計
約半世紀の間に土砂で埋まって見えなくなった水システムの形を読み解き復元する。石井樋の復元設計は、復元の基本となる手がかりを見つけていく作業であったといってもよい。中の島を軸に水システムをとらえる。復元設計の基本をそこにおいた。
■測量図を読む
設計の手がかりを得るためによく眺めていたのが図5(平成7年度測量平面図)である。古図ではないが、現役で使われていた約50年前の姿(400年前につながる)を推測するための有用な情報が詰まっている。
図5:設計検討段階でよく眺めていた測量平面図。中の島を軸に据えることによって水システムの形が浮き彫りになった。石井樋(樋門)直上流の直角に曲がった護岸が「出鼻」であるという発見もこの図からヒントを得た。
■標高10m
測量図から「標高10m」に着目した。図5で言うと、中の島の形を縁取りした青いラインが標高10mである。この標高を基本にして導水路と放水路の縁に青い線を入れる。そうすると、標高10mを基本とした導水路・放水路の平面形が見えてくる。天狗の鼻や象の鼻、導水路左岸の石積など発掘調査で確認された既設構造物の天端高さは標高10~11mであり、河畔林の根元の高さもおおむねこの範囲にある。したがって、石井樋を築造した当時の河岸(天端)は、標高10~11メートルの範囲にあったと推定できるのである。
この等高線をよりどころとして河道を掘削することとした。既往設計では、川幅は一律、河岸は一律2割勾配、その結果河畔林はすべて伐採という内容であった。発掘調査では左岸の一部で石積が確認されており、右岸(中の島)側には石積がない。左岸側は3分勾配の石積とし、河畔林をすべて残した。河畔林も保全継承すべき歴史遺産である。
写真8:復元した導水路(上流側から下流方向)。左岸側は3分勾配の石積とし、河畔林はすべて残した。写真右側手前が天狗の鼻、その奥の出っ張りが「アラコ(荒籠)」である。
図6:導水路立面図。石積天端を標高10~11mに設定。河畔林をすべて残す。
■出鼻の発見
川幅に着目すると、2カ所狭いところがある(図5)。それは、大井手堰の軸線上に設置されたアラコ(荒籠:水制工)と石井樋(樋門)の直上流に設けられた「出鼻」である。象の鼻と天狗の鼻は有名だが、出鼻は知られていない。この位置で導水路の幅を極端に狭めているのはなぜか?、護岸が直角に折れ曲がっているのはなぜか?
「疏導要書」(南部長恒著、天保5年)を読み直すと「出鼻」の記述がある。出鼻は象の鼻や天狗の鼻と並ぶ「鼻」として設置されたと考えられる。この機能を確認するため、水理模型実験(建設技術研究所)を行った。出鼻によって洪水流が中の島側に寄せられ、放水路に向かうことが確認された。出鼻の形(出っ張り)は、洪水(土砂)を嘉瀬川本川に導く形である。これを別な視点から見ると、出鼻が突き出すことによって石井樋が後方に位置することになり、洪水流が石井樋を直撃するのを避けるという意味を持つ。石井樋は堤防をくりぬいて設置しているので堤防が壊れるリスクが高い。そのリスクを最小化するための工夫である。
既往設計では、この出鼻の直角構造が考慮されず、なめらかな河道線形となっていた。実施設計では、出鼻の直角折れ曲がり構造を継承保全することとした。
写真9:復元した出鼻(写真左側)とその奥に位置する石井樋(3連樋門)。出鼻の突き出しによって洪水は放水路(写真右方向)に誘導される。洪水が石井樋(堤防)を直撃しないようにしている。
■象の鼻とノコシ(野越)
前号で述べたように、象の鼻は導水路に洪水(土砂)が流入するのを軽減する目的で設置されたと考えられている。そして、象の鼻根元に設けられたノコシ(象の鼻の天端より1.5mほど低い越流堤)は、象の鼻本体にかかる水勢を逃がして壊れにくくすること、象の鼻先端部を回り込んでくる洪水(土砂)を弱める機能を持っている。
象の鼻は、本体の周りを新しい石積護岸で保護し、上部を空石積みで覆うことになった。野越の復元方法を検討するために、水止め(砂止め)として最も効果的な高さを水理模型実験で検証した。その結果、既存の野越の高さに設定したときに、導水路内への土砂流入が最も少なくなることが確認された。この結果を受けて、既存の野越の高さを変えずに補修復元することとした。
写真10:復元した象の鼻・ノコシ(野越)。
■大井手堰の新設復元
大井手堰は当初ラバー堰(ゴムの袋を空気で膨らます構造)で計画されていた。堰の機能は回復するにしても、歴史的構造物の復元にはほど遠い。石井樋の施設群の中では最も大きい(幅90m)から、石井樋の復元整備の質に関わる。島谷所長(当時)が真っ先に取り組んだのが。大井手堰の設計見直しである。大井手堰の新設復元設計は、日本工営の逢澤さんが担当した。
大井手堰は石造の固定堰であるが、一体的な構造物ではなく戸立(水通し)で分節されていた(写真11、写真12)。普段は角落としで川の水をせき上げ、洪水時には板を外して洪水を逃がす構造である。この戸立て構造を基本にして、角落とし部を起伏ゲートとし、ゲート部を除く堰本体は空石積み構造で新設復元することになった。また、当初は、大井手堰の元の位置より70mほど下流に計画されていたが、元の位置に復元することになった。
写真11(左):昭和初期の大井手堰(佐賀土地改良区所蔵)
写真12(右):昭和30年代の大井手堰。石積が壊れないようコンクリートで覆った(佐賀土地改良区所蔵)
写真13:新設復元された大井手堰。戸立て(水通し)は起伏式ゲート。堰本体は空石積み。
■エントランス空間
エントランス空間は、以前より2~3m程度高い地盤に整地されており、かつての地形構造を伺うことはできない。ここには、石井樋記念館(佐賀水ものがたり館)や駐車場、遊歩道などが計画されているが、旧堤防のラインを基本に動線を設定し、施設配置や地形処理を行った。
写真14:エントランス広場から見た中の島。写真左の古木は多布施川旧堤防のムクノキ。地盤処理をやり直して保全した。
写真15(左):光安福造「石井樋風景」:昭和初期。船着き場や茶屋がある。
写真16(右):復元後の石井樋下流船着き場。
写真17:復元後の放水路(下流側から上流方向)。左側が中の島。河畔林を保全することが可能なように地形処理を行った。
おわりに
ものの形や空間の構造には意味がある。空間の持つ意味を読み解き、大事にすべきもの、基盤になっているものを継承するという姿勢が重要である。石井樋の復元設計は、空間の履歴を読み解く作業であったといえる。
エントランス空間に立つと、中の島の風景(島の形と樹木群)が印象的である。この風景は、石井樋という水システムによって形成された「治水の風景」といえるだろう。そこには、川と人の関わりの履歴が深く刻まれている。
エンジニア・アーキテクトのしごと
- 2014.05.16
- 16|人が歩く道の橋に魅せられて
- 松井 幹雄(大日本コンサルタント(株)|EA協会)
- 2013.12.18
- 15|施工と構造の融合 -Structural Eleganceの追求-
- 春日 昭夫(三井住友建設㈱|EA協会)
- 2013.10.14
- 14|都市のウォーターフロントの意味
- 2013.08.10
- 13|都市デザインの仕事 −40年間をふりかえる−
- 田中 滋夫((株)都市デザイン|EA協会)
- 2013.06.10
- 12|地方都市のデザイナー、エンジニア・アーキテクトの悩み
~地方都市で若手は育つか - 酒本 宏((株)KITABA|EA協会)
- 2013.03.18
- 11|「人を繋げ、プロジェクトを動かす」という“しごと”
- 辻 喜彦(合同会社アトリエT-Plus建築・地域計画工房|EA協会)
- 2013.02.11
- 10|富田大橋のデザイン
- 今度 充之(東京コンサルタンツ(株)|EA協会)
- 2012.11.09
- 09|「空間を繋げて、人の行動を変える」
- 高松 誠治(スペースシンタックス・ジャパン(株)|EA協会)
- 2012.09.20
- 08|「建築を規定するもの」
- 川添 善行(東京大学 生産技術研究所/空間構想一級建築士事務所|EA協会)
- 2012.07.31
- 07|エンジニア・アーキテクトが展開するマネジメント・コンサルティング
- 関口 佳司(関口佳司マネジメント・コンサルタント&景観研究所|EA協会)
- 2012.06.12
- 05-3|別府港海岸の整備と里浜づくり その3
- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)
- 2012.02.01
- 06-3|文化的景観保全とまちづくり その3:熊本県上益城郡山都町における文化的景観保全の取り組み
- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)
- 2012.01.01
- 06-2|文化的景観保全とまちづくり その2:熊本県天草市における文化的景観保全の取り組み
- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)
- 2011.12.01
- 05-2|別府港海岸の整備と里浜づくり その2
- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)
- 2011.12.01
- 06-1|文化的景観保全とまちづくり その1:文化的景観保全における地域マネジメント技術の重要性
- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)
- 2011.10.01
- 05-1|別府港海岸の整備と里浜づくり その1
- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)
- 2011.09.01
- 03-3|「通潤用水下井手水路の改修」その3:工事中の監理と施工結果
- 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)
- 2011.08.01
- 04|堀川運河の修復・整備-土木遺産保存事例①-
- 矢野 和之((株)文化財保存計画協会|EA協会)
- 2011.08.01
- 03-2|「通潤用水下井手水路の改修」その2:課題と解決方針 ~文化景観と自然環境の改変を抑え、人工物の印象を小さくするために、技術的に裏付けながら設計方針を整理する~
- 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)
- 2011.08.01
- 02-4|熊本駅周辺の都市デザイン その4:主役たちのデザイン
- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)
- 2011.07.01
- 03-1|「通潤用水下井手水路の改修」その1:守るべきもの
~幕末の地域自治による野心的プロジェクトが残した水路網の風景と生態系と自治的管理組織~ - 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)
- 2011.07.01
- 02-3|熊本駅周辺の都市デザイン その3:水辺のデザイン
- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)
- 2011.06.01
- 02-2|熊本駅周辺の都市デザイン その2:街路のデザイン
- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)
- 2011.06.01
- 01-3|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その3(最終回)
- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)
- 2011.05.01
- 02-1|熊本駅周辺の都市デザイン その1:考え方について
- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)
- 2011.05.01
- 01-2|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その2
- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)
- 2011.04.01
- 01-1|空間の履歴を読み解く-嘉瀬川・石井樋の復元設計 その1
- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)
吉村 伸一Shinichi Yoshimura
(株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長
資格:
技術士(建設部門:河川、砂防および海岸海洋)
技術士(環境部門:自然環境保全)
特別上級土木技術者[流域・都市](土木学会)
略歴:
1948年 北海道生まれ、石狩川流域人
1971年 室蘭工業大学土木工学科卒業
1971年 横浜市役所 勤務
1998年 吉村伸一流域計画室設立、代表取締役
主な受賞歴:
2005年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(和泉川/東山の水辺・関ヶ原の水辺)
2008年 土木学会デザイン賞 優秀賞(嘉瀬川・石井樋地区歴史的水辺整備事業)
2011年 土木学会デザイン賞 優秀賞(いたち川の自然復元と景観デザイン)
2018年 土木学会デザイン賞 優秀賞(伊賀川 川の働きを活かした川づくり)
2021年 復興デザイン会議第3回復興設計賞(川原川・川原川公園)
2022年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(川原川・川原川公園)
主な著書:
日本文化の空間学(東信堂、2008、共著)
多自然型川づくりを超えて(学芸出版社、2007、共著)
多自然川づくりポイントブック(日本河川協会、2011、共著)
図説・日本の河川(朝倉書店、2010、共著)
川の百科事典(丸善、2009、共著)
川・人・街-川を活かしたまちづくり(山海堂、2001、共著)
自然環境復元の技術(朝倉書店、1992、共著)
組織:
(株)吉村伸一流域計画室
代表取締役 吉村伸一
〒245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台9-1-12-103
TEL:080-5414-7135
業務内容:
・河川の自然復元および景観デザインに関わる研究、計画、設計
・川づくり、まちづくりに関わるコンサルタント業務
・市民参加、合意形成マネジメント
・その他上記に付帯する業務
SPECIAL ISSUE
- 2018年 新年のご挨拶
2018.01.13
地域のためのデザイン/理にかなっているか/統合して考える
- 2014年 新年のご挨拶
2014.01.16
年頭に当たって
- 2013年 新年のご挨拶
2013.01.17
年頭にあたって-善福蛙の夢-
SERIAL
- 土木デザインノート
2015.07.21
09|川・水辺のデザインノート
- 土木デザインノート
2014.06.27
08|川・水辺のデザインノート
- 土木デザインノート
2014.02.26
07|川・水辺のデザインノート
- 土木デザインノート
2013.10.23
06|川・水辺のデザインノート
- 土木デザインノート
2013.07.11
05|川・水辺のデザインノート
- 土木デザインノート
2013.05.02
04|川・水辺のデザインノート
- 土木デザインノート
2013.02.06
03|川・水辺のデザインノート
- 土木デザインノート
2012.11.25
02|川・水辺のデザインノート
- 土木デザインノート
2012.10.01
01|川・水辺のデザインノート
- エンジニア・アーキテクトのしごと
2011.06.01
01-3|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その3(最終回)
- エンジニア・アーキテクトのしごと
2011.05.01
01-2|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その2
- エンジニア・アーキテクトのしごと
2011.04.01
01-1|空間の履歴を読み解く-嘉瀬川・石井樋の復元設計 その1
WORKS