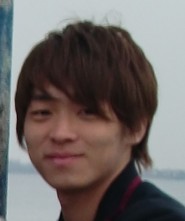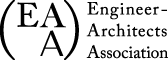/ all
/ all
2011.04.01
01|模型をつくる意味
二井 昭佳(国士舘大学|EA協会)
西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
安田 尚央(国士舘大学工学研究科建設工学専攻)
■なぜ模型が必要なのか
土木の世界では、計画や設計の際に模型を用いることがほとんどない。それどころか、模型はあくまでも風洞実験や水理実験に使うもので、それ以外の場合に模型を造るのは、設計者の単なる自己満足に過ぎないと思われている。
しかし、これは他のものづくりの分野から見ると異様な状況である。プロダクトの世界、例えば車の設計でいえば、初期の段階ではスケッチによって案が練られるが、ある段階からは4分の1の大きさのクレイモデルを作成し、最終的には原寸大のモックアップを用いて検討するのが普通である。また、同じ建設分野である建築の世界でも、数百分の1の敷地模型から10分の1程度の部分模型まで,設計の段階に応じてさまざまな縮尺の模型を作成する。つまり、他のものづくりの分野では模型を造るのが当たり前だと考えられているのだ。
なぜ、彼らが模型を造るのか。それは、検討の段階から最終的なかたちをきちんと把握するためだ。図面やスケッチといった2次元の情報ではどうしても細かい取り合わせが分かりにくいし、完成イメージもあやふやになりがちである。車にしても建築物にしても決して安いものではない。製作途中に不具合が発生したり、クライアントのイメージと異なるものが出来上がったりすれば大問題になる。そこで、3次元の情報が得られる模型の出番となる。
土木が造るものは、車や建築物などよりも遥かに施工費が大きい。しかも、複雑な地形に収めなくてはならないし、行政担当者や最終的なクライアントである市民と完成イメージを共有する必要もある。だから本当は、土木にこそ模型が必要であり、発注者はすべての事業で設計者に模型の作成を求めるべきだと考える(もちろん、それに必要な経費は払うべきであるが、全体の施工費からみればごく少額であり、結果的には安い買い物になるはずだ)。
ただ上記のような模型の重要性が理解されたとしても、これまで土木分野に対応した模型に関する書籍はなく、その作り方はほとんど知られていないのが現状である。そこで本連載では、土木分野に合わせた模型の基本的な作り方を1年間に渡って解説する。ささやかな試みだが、土木の世界にも模型を造るのが当たり前という文化が根づくことを願って努力したい。(二井)
■模型を作る上で大切なこと ~「誰に何をどのように伝えるか?」
模型を作ることの必要性については、前半で二井さんが述べた。ここでは模型を作る上で意識すべき大切なことについて、私なりの考えを記しておきたい。
事務所を始めて間もない頃、公園の計画案を模型にして、地元の方々に見て頂いた時の話である。我々は、緩やかな起伏のある芝生広場に人々が座っている情景を模型に表現し、柔らかい芝生広場のイメージを伝えようとしていた。地形を表現する際によく用いられる方法ではあるが、コンターと呼ばれる等高線毎にスチレンペーパーを切って積み重ね、その起伏を表現していた。厚みのある材料を重ねているため段差がどうしても出てしまうのであるが、参加していた地元のおばあさんからこんなことを聞かれた。「この部分は階段のようになっていて座れるのですか?」と。もちろん滑らかな芝生の斜面として計画していたので、その旨を補足説明したが、もし言葉で説明をする機会がなければ、おばあさんにはずっと誤解されたままであったであろう。
何が問題であったか?もちろん誤解をしたおばあさんが悪い訳ではない。「模型を見慣れていない地元の人」に「滑らかな芝生広場のイメージ」を伝えようとしていたにも関わらず、段差の生じる表現を用いたところに問題があったのだ。「滑らかな芝生広場のイメージ」を伝えようとするのであれば、段差のない表現をすべきであったのである。
地元の方々に見て頂いた模型(公園の芝生には段差が見える) (片山津温泉砂走公園計画模型 EAU作成)
模型は、誰かに伝えたいことを伝えるための一つのツールであり、作ることで満足し、それが目的化してしまってはならない。模型はあくまでも手段であり、「誰に何をどのように伝えるか」ということをよく考え、それにふさわしい模型表現を選ばなければならない。(文章でも、自分だけが分かれば良いメモと、好きな人の事を想って書くラブレターでは、文字の書き方や文章の表現が変わるのは当然である。)また場合によっては、模型という手段ではなく、スケッチやCGといった別の手段を用いた方がふさわしい場合もある。
何かを伝える手段という点から考えると、模型は大きく二つに分けることができる。
一つはスタディ模型と呼ばれる模型で、もう一つはプレゼン模型と呼ばれるものである。
スタディ模型は、文章で言えばメモのようなもので、考えるための模型である。自分(又は設計チームのメンバー)に確認したい内容が伝われば良く、確認したい内容以外は簡略化して作る場合が多い。むしろ多くの案を検討するために、手早くまた多くの模型を作ることが求められる。場合によっては、簡単に作り変えられるように、意図的に壊しやすく作る時もある。
プレゼン模型は、文章で言えば手紙のようなもので、伝えるための模型である。模型を見慣れていない地元の方々に見せる場合と、模型や現場を見慣れている工事関係者に見せる場合とでは、選ぶべき模型表現は異なる。
スタディ模型の例:周辺地形と広場の関係を確認するための模型 (S防災広場スタディ模型1/1000 EAU作成)
プレゼン模型の例 専門家の委員会へ提示したプレゼン模型(広場の柔らかな地形のデザインを強調) (S防災広場スタディ模型1/250 EAU作成)
いずれの模型にしても、「誰に何をどのように伝えるのか」によって模型の作り方は変わってくる。スケール(模型の縮尺)、模型の範囲、各部のパーツ(地形、樹木、水、建物など)、色彩などは連動して変わる。また見てもらいたい部分を強調するために、細かく作り込む部分とあえて簡略化して作る部分を分ける場合もある。
次号以降では、模型の表現を決める上で考えなくてはならないことを紹介し、その後各部の具体的な模型表現を紹介していきたいと思う。(西山)
■模型作りを担当します
はじめまして。本連載では主に模型製作を担当いたします。実際に模型を作り、紹介するなかで自分自身も再勉強したいと考えています。よろしくお願いします。(安田)
ドボクノモケイ
- 2012.08.20
- 13|いよいよ完成 その2 ~模型写真を撮ろう!+あとがき
- 二井 昭佳(国士舘大学|EA協会)
西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2012.07.12
- 12|いよいよ完成 その1 ~忘れちゃいけない最後の仕上げ
- 西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2012.05.30
- 11|モケイづくりを始めよう その8 ~構造物について
- 西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2012.04.21
- 10|モケイづくりを始めよう その7~人の表現
- 西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2011.12.01
- 09|モケイづくりを始めよう その6~水の表現
- 西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2011.11.01
- 08|モケイづくりを始めよう その5~植栽の表現
- 西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2011.10.01
- 07|モケイづくりを始めよう その4~建物の表現
- 西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2011.09.01
- 06|モケイづくりを始めよう その3~敷地の表現
- 二井 昭佳(国士舘大学|EA協会)
西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2011.08.01
- 05|モケイづくりを始めよう その2~地形の表現
- 西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2011.07.01
- 04|モケイづくりを始めよう その1~ベースをつくる
- 二井 昭佳(国士舘大学|EA協会)
安田 尚央(国士舘大学工学研究科建設工学専攻)
- 2011.06.01
- 03|模型の鉄則その2~表現したいイメージを決めよう
- 西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
- 2011.05.01
- 02|模型の鉄則その1~作成範囲とスケールを決めよう
- 二井 昭佳(国士舘大学|EA協会)
西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
安田 尚央(国士舘大学工学研究科建設工学専攻)
- 2011.04.01
- 01|模型をつくる意味
- 二井 昭佳(国士舘大学|EA協会)
西山 健一((株)イー・エー・ユー|EA協会)
安田 尚央(国士舘大学工学研究科建設工学専攻)
二井 昭佳Akiyoshi Nii
国士舘大学|EA協会
資格:
博士(工学)
略歴:
1975年 山梨県生まれ
1998年 東京工業大学工学部社会工学科 卒業
2000年 東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻修士課程 修了
2000年 アジア航測㈱ 入社(道路・橋梁部所属)
2004年 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻博士課程 入学
2007年 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻博士課程 修了
博士(工学)
2007年 国士舘大学理工学部都市ランドスケープ学系専任講師
2012年 スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH Zurich)guest professor
2013年 国士舘大学理工学部都市ランドスケープ学系准教授
2014年 国士舘大学理工学部まちづくり学系准教授
主な受賞歴:
2006年 第8回「まちの活性化・都市デザイン競技」奨励賞
2007年 景観開花。「道の駅」佳作
2009年 広島南道路太田川放水路橋りょうデザイン提案競技(国際コンペティ
ション)最優秀賞
篠原修・内藤廣・二井昭佳編「GS軍団連帯編 まちづくりへのブレイクスルー 水辺を市民の手に」、彰国社、2010
組織:
国士舘大学 理工学部
〒154-8515 東京都世田谷区世田谷4-28-1
TEL:03-5481-3252(理工学部事務室)
HP:http://www.kokushikan.ac.jp/faculty/SE/laboratory/detail.html?id=107007
SPECIAL ISSUE
- 橋梁デザインのゆくえ
2012.12.18
場を繋ぎ、場を創る橋を目指して
SERIAL
- ドボクノ手習い-土木系大学のデザイン演習
2016.05.30
06 | “どこに手を打つか”から考える
−国士館大学理工学部まちづくり学系
「公共空間デザイン演習」−- EAプロジェクト100
2015.08.18
10|牛久駅東口駅前広場(前半)
- 風景エッセイ
2012.10.30
09 |共同体の意思が生み出す風景
- ドボクノモケイ
2012.08.20
13|いよいよ完成 その2 ~模型写真を撮ろう!+あとがき
- ドボクノモケイ
2011.09.01
06|モケイづくりを始めよう その3~敷地の表現
- ドボクノモケイ
2011.07.01
04|モケイづくりを始めよう その1~ベースをつくる
- ドボクノモケイ
2011.05.01
02|模型の鉄則その1~作成範囲とスケールを決めよう
- ドボクノモケイ
2011.04.01
01|模型をつくる意味
NEWS

2019.07.01
『まちを再生する公共デザイン — インフラ・景観・地域戦略をつなぐ思考と実践』
WORKS

西山 健一Kenichi Nishiyama
(株)イー・エー・ユー|EA協会
資格:
技術士(建設部門:都市および地方計画)
略歴:
1975年 東京都生まれ
1998年 東京大学工学部土木工学科卒業(景観デザイン)
2000年 東京大学大学院社会基盤工学専攻修士課程修了(景観デザイン)
2000年〜2002年 (株)日本設計勤務
2002年 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 博士課程入学
2003年 (有)イー・エー・ユー設立
2005年 東京大学大学院社会基盤工学専攻博士課程中退(景観デザイン)
2005年〜2007年 国土交通省東北地方整備局 景観デザイン研修講師
主な受賞歴:
2008年 土木学会デザイン賞 奨励賞(片山津温泉砂走公園)
2009年 広島南道路太田川放水路橋りょうデザイン提案競技(国際コンペティ
ション)最優秀賞
2013年 土木学会田中賞(各務原大橋)
2014年 土木学会田中賞(太田川大橋)
2015年 土木学会デザイン賞 優秀賞(各務原大橋)
2016年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(太田川大橋)
組織:
(株)イー・エー・ユー
代表取締役 崎谷 浩一郎
〒113-0033 東京都文京区本郷2-35-10本郷瀬川ビル1F
TEL:03-5684-3544
FAX:03-5684-3607
業務内容:
・土木一般、建築、造園等に関わる景観デザイン、設計、コンサルタント業務
・都市開発、都市計画、まちづくりに関わるコンサルタント業務
・その他上記に付帯する業務
SERIAL
- ドボクノモケイ
2012.08.20
13|いよいよ完成 その2 ~模型写真を撮ろう!+あとがき
- ドボクノモケイ
2012.07.12
12|いよいよ完成 その1 ~忘れちゃいけない最後の仕上げ
- ドボクノモケイ
2012.05.30
11|モケイづくりを始めよう その8 ~構造物について
- ドボクノモケイ
2012.04.21
10|モケイづくりを始めよう その7~人の表現
- ドボクノモケイ
2011.12.01
09|モケイづくりを始めよう その6~水の表現
- ドボクノモケイ
2011.11.01
08|モケイづくりを始めよう その5~植栽の表現
- ドボクノモケイ
2011.10.01
07|モケイづくりを始めよう その4~建物の表現
- ドボクノモケイ
2011.09.01
06|モケイづくりを始めよう その3~敷地の表現
- ドボクノモケイ
2011.08.01
05|モケイづくりを始めよう その2~地形の表現
- ドボクノモケイ
2011.06.01
03|模型の鉄則その2~表現したいイメージを決めよう
- ドボクノモケイ
2011.05.01
02|模型の鉄則その1~作成範囲とスケールを決めよう
- ドボクノモケイ
2011.04.01
01|模型をつくる意味
WORKS
安田 尚央Takahiro Yasuda
国士舘大学工学研究科建設工学専攻
1988年生まれ。岐阜県出身。
国士舘大学理工学部都市ランドスケープ学系を卒業後、大学院に在籍。二井研究室所属。学部3年生の時からイー・エー・ユーにて模型アルバイトに取り組む。
SERIAL
- ドボクノモケイ
2011.07.01
04|モケイづくりを始めよう その1~ベースをつくる
- ドボクノモケイ
2011.05.01
02|模型の鉄則その1~作成範囲とスケールを決めよう
- ドボクノモケイ
2011.04.01
01|模型をつくる意味