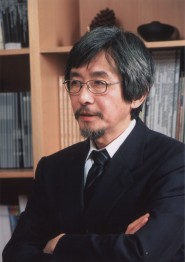/ all
/ all

2012.05.10
南雲さんとの出会いの頃
篠原 修(GSデザイン会議|EA協会 会長)
南雲勝志さんとの出会いは、平成の初めの頃、皇居周辺道路の検討委員会の席上だった、らしい。らしい、というのは僕が全く憶えておらず、南雲さんにそう断言されたからである。皇居周辺道路の検討委員会は建設省の東京国道事務所が音頭を取って、東京都、千代田区がこれに加わり、三者が統一的に皇居周りの道路をデザインしようという、なかなかに良い企画の委員会であった。通常であれば道路の整備は管理者毎に行なわれ、相互の連携はないのである。委員会を立ち上げて、国道、都道、区道の壁を取り払おうとしたのである。委員長は中村良夫さん、僕は幹事長だった。デザインの実務を担当したのがアプル総合計画事務所で、中野恒明さんがボスである。アプルには僕の教え子の重山陽一郎がいて、彼がこのプロジェクトの担当者だった。南雲さんは中野さんに呼ばれて、照明のデザインを受け持っていた。
その何回目かの席上で南雲さんが三案を示し、どうでしょうと言った所、委員会はシーンとしてなんの反応もなかった、とは南雲さんの回想である。困りましたよ、本当に、と彼は当時を思い出しながら僕に言うのである。で、どうなったんだっけ、と聞くと、篠原先生が次のように言ったのだと言う。三案はどれをとっても合格のラインに達しています。南雲さんのお勧めは、と続いたのです。よく憶えているものだと思う。誰も何にも言ってくれないので、ドキドキしたんでしょうね。この委員会の成果が、今や照明柱の古典となっている鳳凰(車道用)、近衛兵(歩道用)の二つのタイプである。
皇居の件では全く記憶に無かったが、浦安の境川のプロジェクトでの南雲さんはよく憶えている。ディズニーランドがある、あの浦安です。但し、旧い方の。境川は古くは山本周五郎の青べか物語の舞台となったことで知られ、新しいところでは、山口瞳がよく寿司を食べに行ったことで有名である。新しくもないか。旧の市街地を東西に流れる境川は、かっては漁港として栄えていた町の中心であった。その上下流に水門が出来たお陰で境川は治水の役目から解放された。パラペットを取り払い、川と両岸の道路を一体的に整備しようというプロジェクトである。事業主体は千葉県と浦安市。計画の実務は、先述のアプルが担当していたのだが、設計の段階になってアプルから独立した小野寺さんが業務を受けていた(この辺りの変更には色々あるのだが、南雲さんには直接関係がないので省略する)。
護岸工事は既に進行中で矢板が打設されていて、それは通常のようにコンクリートを載せる仕様になっていた。荷重の点で、もはや石積みには出来ない。かといって、コンクリートではね、というのが皆んなの思いだった。小野寺さんが考えたのはレンガだった。既製品と特注で焼いたレンガを並べ、半年の間、曝露試験を実施した。この荷重の点からレンガにというやり方は、桑名の住吉入江でも再び実行されたやり方である。僕の役割は委員会の委員長である。ある日の事、小野寺さんに案内されて現場を見に行った。レンガの護岸はうまく仕上がっていて、これはいい、合格点。橋の袂に差し掛かると妙な照明柱が立っているではないか。これは、と聞くと、何でもデンマーク製のものなのだと答える。デンマークだかなんだかしらないが、シャンプーハットの如きのものなのである。シャンプーハット、分かりますか? 子供の頭を洗う時に頭にかぶせる、あれです。小野寺さんはどうもかぶれやすい、いや失礼、かぶれやすかった。見ていいと思うとすぐに飛びつくのである。どっかで見たんでしょう。彼の出身校がある茂原の川のプロジェクトでも、インドネシアだかなんだか知らないが、妙に黄色じみた自然石を外国から持ち込んできて往生した事があった。完全に房総の風土から浮いているのだ。あれは失敗でしたね、大分経ってからの本人の弁。
浦安の境川がシャンプーハットだらけになってはかなわない。南雲君にやってもらおうよ。意外にもあっさり承知した。本人も、これはまずいかな、と内心では思っていたのだろう。南雲さんが入って、ここから広場、街路をデザインする小野寺と南雲のゴールデンコンビがはじまるのである。照明はもう安心である。何の心配もいらない。驚いたのは、転落防止の柵の図面を見た時だった。水面への透過性を高めるのだと言って、極めて細い部材を使っているのである。強度は計算しているからOKなのだろうが、いかにも頼りない。これで不安にならないか、散歩する人間の身になってみなよ。大丈夫ですよ。本当?出来上がって実物を見るとその通りなのだった。大丈夫なのだ。図面と実物の対応は南雲の中では正確についていたのである。
これ以降、南雲さんには注文はつけない事にしている。任せておけばよいのだ。一緒にやるにこんなに楽なパートナーはいない。
不思議なのは、南雲さんのようなデザイナーが新潟県は六日町のごとき田舎から出た事である。八海山の麓です。絵や音楽のような純粋芸術は別として、建築、造園、グラフィックス、プロダクトなどのデザインは都会育ちでなくては、というのが定説なのである。例外は今治出身の丹下健三。ソリの形とか言っている有名彫刻家は田舎の出身で(何処だかわかりますか)、道理で、と思った人も多いでしょう。
大酒飲みの南雲の生態、女性好きの(但し30代までか)南雲、スギダラに見るリーダーとしての南雲、ダジャレの南雲など語ることには事欠かないが、それは誰かが書いてくれるでしょう。では、この辺で。
追。南雲さんとヨシモトポールのデザイン開発に付いては、5月から連続対談を企画しています。いずれ記録として出すつもり。乞う御期待。
モノづくりから始める地域づくり-南雲勝志の方法
- 『もの』と『人』が「こと」をおこし、場が豊になる。
南雲勝志の内から外への眼差しと行動 - 川上 元美((有)川上デザインルーム代表)
- 『もの』と『人』が「こと」をおこし、場が豊になる。
- 地区の将来をデザインする
- 植村 幸治(宮崎県日向土木事務所)
- 南雲さんとの出会いの頃
- 篠原 修(GSデザイン会議|EA協会 会長)
- 楽しくなければスギダラじゃない!
- 菅原 香織(秋田公立美術大学 美術教育センター|EA協会)
篠原 修Osamu Shinohara
GSデザイン会議|EA協会 会長
資格:
工学博士
略歴:
1968年 東京大学工学部土木工学科卒業
1971年 東京大学工学系研究科修士課程修了
1971年 (株)アーバン・インダストリー勤務
1975年 東京大学農学部林学科助手
1980年 建設省土木研究所研究員
1986年 東京大学農学部林学科助教授
1989年 東京大学工学部土木工学科助教授
1991年 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授
2006年 政策研究大学院大学教授、東京大学名誉教授
主な受賞歴:
1986年 国立公園協会 田村賞
1990年 土木学会田中賞(森の橋・広場の橋)
1996年 土木学会田中賞(東京湾横断道路橋梁)
2000年 土木学会デザイン賞優秀賞、土木学会田中賞(阿嘉橋)
2000年 土木学会出版文化賞「土木造形家 百年の仕事-近代土木遺産を訪ねて」
2001年 土木学会デザイン賞 最優秀賞、土木学会田中賞(新港サークルウォーク)
2002年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(阿嘉橋、JR中央線東京駅付近高
2004年 土木学会田中賞(朧大橋)
2004年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(陣ヶ下高架橋)
2004年 グッドデザイン賞 金賞(長崎・水辺の森公園)
2005年 土木学会田中賞(謙信公大橋)
2006年 土木学会出版文化賞「土木デザイン論-新たな風景の創出をめざして-」
2007年 土木学会田中賞(新西海橋)
2008年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(苫田ダム空間のトータルデザイン)
2008年 土木学会田中賞(新豊橋)
2008年 ブルネル賞(JR九州 日向市駅)
2008年 日本鉄道賞ランドマークデザイン賞(JR四国 高知駅)
2009年 鉄道建築協会賞停車場建築賞(JR四国 高知駅)
2010年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(新豊橋)
主な著書:
1982年「土木景観計画」、技報堂出版
1985年「街路の景観設計」(編、共著)、技報堂出版
1987年「水環境の保全と再生」(共著)、山海堂
1985年「街路の景観設計」(編、共著)、技報堂出版
1991年「港の景観設計」(編、共著)、技報堂出版
1994年「橋の景観デザインを考える」(編)、技報堂出版
1994年「日本土木史」(共著)、技報堂出版
1999年「土木造形家百年の仕事」、新潮社
2003年「都市の未来」(編、共著)、日本経済新聞社
2003年「土木デザイン論」、東京大学出版会
2005年「都市の水辺をデザインする」(編、共著)
2006年「篠原修が語る日本の都市 その近代と伝統」
2007年「ものをつくり、まちをつくる」(編、共著)
2008年「ピカソを超える者はー景観工学の誕生と鈴木忠義」、技報堂出版
組織:
GSデザイン会議
東京都文京区本郷6-16-3 幸伸ビル2F
TEL:03-5805-5578
FAX:03-5805-5579
SPECIAL ISSUE
- 2024年 新年のご挨拶
2024.01.17
今年はパリの年、エッフェルの年
- 2023年 新年のご挨拶
2023.01.18
エンジニア・アーキテクト集団の社会的認知
- 2022年 新年のご挨拶
2022.01.17
景観の履歴と今後、歴史感覚を持って
- 2021年 新年のご挨拶
2021.01.23
コミュニケーション
- 2020年 新年のご挨拶
2020.01.31
本来の景観に立ち帰って
- 2019年 新年のご挨拶
2019.01.22
古希を過ぎての脱皮なるか
- 2017年 新年のご挨拶
2017.01.04
世を変えられる、とまでは言わないが、世は変わる
- 2016年 新年のご挨拶
2016.01.31
自然の偉大さ
- 2015年 新年のご挨拶
2015.01.13
エンジニア・アーキテクトで土木を立て直そう
- 2014年 新年のご挨拶
2014.01.16
「防災」には「景観」が不可欠の相方である
- 2013年 新年のご挨拶
2013.01.17
新年のご挨拶
- re-edit 遅い交通がまちを変える
2012.08.29
都市交通の再びの多様化、分離と混合の政策
- モノづくりから始める地域づくり-南雲勝志の方法
2012.05.10
南雲さんとの出会いの頃
- 震災特別号
2012.04.30
郷土の誇りとなる公共のデザインを
―復旧、復興担当者に望む―
- 復興元年を迎えて
2012.04.10
これから本格化する復興デザインに向けて
その1:復興に使用する材料
- 2012年 新年のご挨拶
2012.01.03
年頭のご挨拶、平成24年
- 復興に向けて大切なこと
2011.11.03
人間生活圏再生に関する生態学的考察
- 祝!平泉、世界遺産登録決定!
2011.09.03
平泉の何を守るのか
- 公共事業のプロポーザル方式を問う
2011.05.01
プロポーザルの評価を考える
- 公共事業のプロポーザル方式を問う
2011.05.01
プロポーザルで選ぶ設計者とアフターケア
- エンジニア・アーキテクト協会、始動。
2011.04.01
エンジニア・アーキテクト協会創立にあたって
SERIAL
NEWS
2017.12.18
【予約注文のお知らせ】篠原修著「河川工学者三代は川をどう見てきたのか(仮題)」

2012.12.27
土木学会景観・デザイン研究発表会投稿論文

2012.12.01
講演録「下僕の下僕という地位を脱する為に」

2012.11.05
「瀬戸内海 No.64」に論説文掲載

2012.09.28
雑誌「道路建設」への寄稿文

2012.06.08
復興まちづくり講習会

2012.06.08
第32回土木史研究発表会

2012.06.08
まちづくりと景観を考える全国大会
WORKS